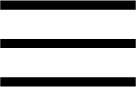健保ニュース
健保ニュース 2025年3月下旬号
出産費用の保険適用
佐野会長代理 保険者は負担増を懸念
一時金引き上げ手法は限界
「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」は19日、出産にかかる妊婦の経済的負担の軽減に向けた保険適用を含む負担軽減策について議論した。
この日の会合で厚生労働省は、出産にかかる妊婦の経済的負担の軽減として、分娩に伴う診療・ケアやサービスのうち、①妊婦の希望にかかわらず提供されるもの②妊婦が希望して選択するもの─をテーマとして提示した。
①は、(1)出産にかかる平均的な標準費用をすべて賄えるようにするとの基本的な考え方に照らし、出産費用に施設間格差が生じている現状(2)出産育児一時金の支給額の引き上げ後も、出産費用が年々上昇している現状(3)保険適用を含む負担軽減策が地域の周産期医療の確保に影響を与えないような方策─への対応を論点とした。
また、これに関連し、石渡勇参考人(日本産婦人科医会会長)は、同医会が昨年5~6月に実施した「産科診療所の経営状況と今後の事業継続の見込みに関する調査結果」を報告した。
調査は、産科診療所の厳しい経営状況を示したうえで、仮に分娩料が現在より一律5万円減少すれば、約2割の施設が赤字に転落すると推計。また、正常分娩の費用が保険適用となった場合、「分娩取扱を中止」「中止を検討」と回答した施設が約6割(785施設中、486施設)にのぼった。
健保連の佐野雅宏会長代理は、①(2)の状況から、「出産育児一時金の引き上げという手法には限界があり、費用負担している現役世代の理解を得られない」と指摘し、別の手法を合わせて検討すべきとの考えを示した。
①(3)の地域の周産期医療の提供体制は、国のインフラ基盤整備に関わる問題と指摘し、「社会保険料財源を使って事業主や被保険者が負担すべきものとは思えない」と断じた。
「出産費用の保険適用をめぐる財源とは切り離して別途解決策を考えるべき」と強調し、「体制確保は、公費(税財源)で賄うべきだ」との考えを改めて示した。
①(1)では、「保険適用の検討は、保険給付範囲の標準化や保険料負担者の納得に応じた内容とすべき」と述べ、「いずれも施設間格差の多い要因把握や費用内訳の見える化が前提になる」との考えを示した。
また、調査報告に対して、保険適用により医療機関の経営悪化が懸念されている状況について質した。
石渡参考人は、「保険適用になった場合、自由度がなくなる」と言及し、「保険点数が高くなれば対応できるが、今までのことを考えると高い点数設定は難しく、会員は収入が落ちると考えるのが一般的だ」と応じた。
濵口欣也構成員(日本医師会常任理事)は、物価上昇や人件費の上昇が続けば経営はさらに悪化すると指摘。「出産費用の保険適用と周産期体制の議論は、切り離し、別途解決策を考えるべき」との考えを示した。
仮に分娩費用の負担が軽減されても、地域に分娩施設が無く、遠方の施設に行かざるを得ない状況になれば、交通費負担という新たな経済的負担が生じると指摘した。
佐野会長代理は、「保険者からは、妊婦の経済的負担を軽減することで保険料負担が増えるのではないかという声がある」との懸念を示し、「医療機関の提供体制と保険料負担者、妊産婦の負担軽減のバランスをどう取るかが重要」と強調した。